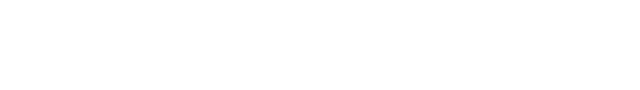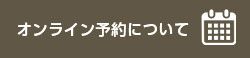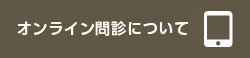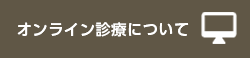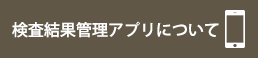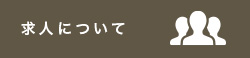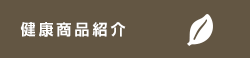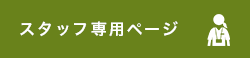R5年度横浜市医師会会長選立候補について→残念ですが落選しました…。
ご挨拶
大久保です。応援をしてくださった方々にまずはお礼を申し上げます。ありがとうございました。票を持っている先生方からも応援のお言葉をたくさんいただきましたが、票を入れるほどまかせられると思ってくださるということもなかったようです。残念ながら令和5年6月10日の選挙では票を全くとることもできずに、188票中わずか16票という結果に終わってしまいました。やはり、一部の先生に直接ご指摘いただいていたように、いままでもそんな感じだったのだから変わることないというお話のとおりで、この件については自らの経験の浅さカンの鈍さが露呈した結果になってしまったなと感じています。以前より、選挙になったら自分は何もわからないだろうなと思っていたのでなるほどと思いました。でも、これも人間社会が動いていくには重要なことというのもわかっております。また、16票はされど16票でもあり、この状況でしっかり私を応援して票の形で示してくださった先生方は今後私が大事にしていかなくてはならない重要な仲間だということも感じています。選挙に負けてもそのアクションに出ることで君は仲間を知るのだから、勇気を持てとのアドバイスも多くの友人よりいただいておりましたし、その通りと思います。
さて、自分としては落選したからといって、ひどく落ち込むこともなく、DX化やコロナ診療といった課題については、大多数の医療機関より少し先を見てしまう性急な部分があり、それが、自分が医師会での業務につまらなさを感じてしまった理由でもありましたし、いったん離れられてほっとしているのも事実です。6年間の市医師会の常任理事の仕事の総括としては自分としては納得がいくものです。今後は、自院での診療にしっかり取り組みながら、何が自分ができるベストなのか、患者さんにとってのベストなのかということをしっかり考えていきたいと思います。
市医師会は私がいなくても、新たな人材が新しい目線で活躍してくれると思います。それは私だったらこうすると思うこともあるかもしれませんし、だいぶ遅いなと感じることもあるでしょうが、周縁から医師として患者さんの診療をしっかり行いながら、見守り、時には場所をいただければ意見を言わせていただくということにしたいと思います。
立候補の要点
① 医師会運営において、職能集団的な運営を脱却し、公益性を目指す
② 忖度に依存した運営をやめ、お互いの主張が明瞭になるように会議を活発化させる
③ 多様性のある医師の参加促進
医療者向けYouTubeチャンネルのWevery!チャンネルに、DX化を推進するためにSEを登用しているクリニックとして取材いただきました。
令和5年6月11日
おおくぼ総合内科クリニック院長、戸塚区医師会副会長
支払基金審査委員
SYMVIEW開発協力(LAYERD)
大久保辰雄
大久保が感じていること…。
自分は人間を診ることが大好きで、全人的な診療をモットーとしていますが、1人の人間をみることだけに拘泥せず、「上医は国を治す」ということも医師として重要な役割と捉えています。これから先は光速で世の中が動いていくので、遅れをとってしまうと、国全体にとっても、医療業界としても得する結果にはなりません。
現在、AIによるシンギュラリティの真っ只中にあって、自由意志が最重要とされる時代は終わりを告げ、倫理を問われる時代が来ると考えられます。AIは個個の人間に対しては意思決定の支援を行うという役割を担っていくと考えられ、医療においても医師の教育より倫理的側面を含有した医療的決断の支援を行うシステムの構築に進んでいくと予想されます。DX化が進むことにより、人間はより人間らしい決断と生活に時間をかけられるようになるのです。
名古屋で開催されたプライマリケア連合学会では次世代医療のセッションがもたれましたが、多くの若い先生方が新しい発想で新たな医療のあり方を模索していました。のんびりゴルフをするのも程々にして、研究会に参加したり、異業種交流会に参加して、積極的にものごとを変えようと考えている人材との交流を拡げるべきではないでしょうか。
Word Powerを信じ、怖気づかずに言葉を発することで、相手の反応を伺いながら、相手の考え方を取り入れて、より良い考え方に思索を深めていくことが初めて可能となるというのが私の行動規範です。
経歴
S58 開成高校卒業(岸田現首相も同窓ということになります)
H元 慈恵医大卒(最終学歴は慈恵医大大学院)
卒後は当時珍しかった全科ローテーションの研修を卒業校の慈恵医大にて修了し、その後研究職をめざして大学院に進学。大学院修了後は外科に入局し、英国聖トーマス病院、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校附属病院などでの留学経験を積んだ。開業医であった父親の遺志をついて地元の方々のための医師となることを決意し、18年間の外科のキャリアを重ねていくことを捨て、内科に転向。大船中央病院総合診療内科にて2年勤務の後、H21に東戸塚におおくぼ総合内科クリニック開院。
自らもクリニックのある東戸塚に住み、自分が住む土地にどれだけ貢献できるかを考え、医師会活動にも参加。H27より戸塚区医師会副会長、H29より横浜市医師会常任理事兼務となり、診療の合間を縫って、横浜市と戸塚区のために、自分の患者さん達のためにできることを利益と関係なく行うというスタンスで活動中。
また、合間を縫って当時まだ医療系1ベンチャー企業に過ぎなかったLAYERDと一緒にウェブ問診「SYMVIEW」の開発を行った。本システムはコロナ下の診療を効率的に進めるための大きな武器となり、横浜市内外の医師会休日診療所での採用が進められている。過去には、まだセキュリティや可能性についても見極めが難しかった平成8年(慈恵医大外科在職時)、大学院卒業時の初職務として、大学を説き伏せ、外科における手術録の共有システム構築に成功している。
クリニックは総合内科・心療内科を柱に掲げ、内科全般を広くみて、不定愁訴や心身症に苦しむ方々の診療を診療の課題のひとつとしている。心療内科については外科在職中より3年間、PIPC(プライマリケア医のための精神科)事業に力を入れる信愛クリニック(大船)に非常勤として勤務し、研鑽を積んだ。